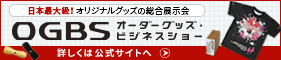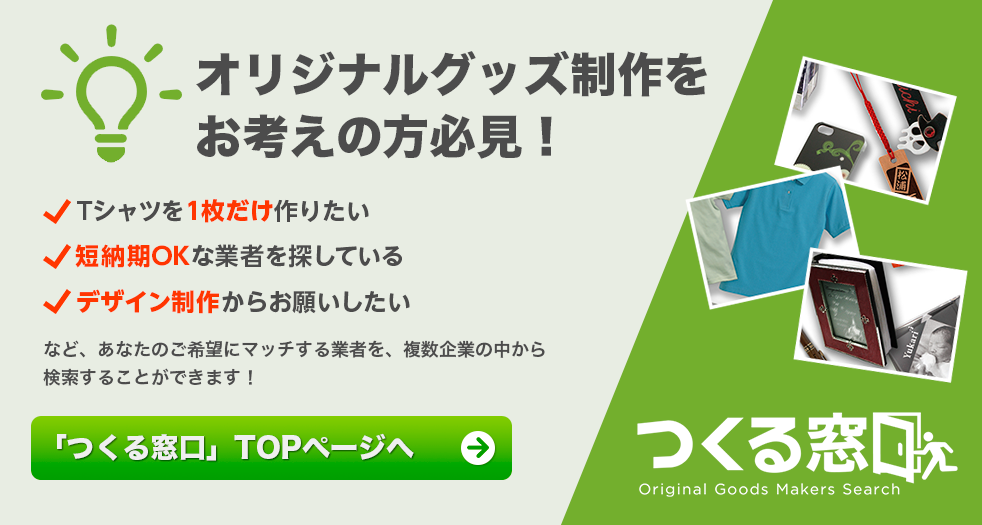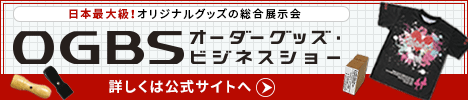近年、スポーツ観戦などでよく使われている「スティックバルーン」を知っていますか?
オリンピックの中継を見ていて、棒状のものを両手に持って、打ち鳴らして応援するサポーターを見かけた!という人も多いかと思います。
その「棒」こそが「スティックバルーン」。「チアスティック」や「応援棒」とも呼ばれています。
長細い棒状の風船が2本1組になった応援グッズで、バルーン同士を叩くことで金属のような甲高い音を鳴らして応援します。
風船の空気封入口に差し込んだストローから空気を入れて膨らませて使うので、メガホンのような鳴り物と違って、空気を抜けば折り畳んで持ち運べるというメリットがあります。
さらに、表面に応援メッセージやチームロゴなどを入れる「名入れ」も人気です。
チームカラーのバルーンにプリントすれば、応援側の団結力も高まり、観戦がより一層盛り上がるはず!
他にも、マラソンなどでは大会名やメッセージに加えて、協賛企業の社名を名入れするなど、販促的な使い方も可能です。
そんなスティックバルーンの名入れについて、もっと詳しく紹介していきましょう。

スポーツ観戦の応援グッズにピッタリ
目次
日本に広まったきっかけは?
もともと欧米を中心に海外で使われていたスティックバルーン。日本に広まったのは2002年、日韓共催のFIFAワールドカップと言われています。
韓国のサポーターがスティックバルーンを日本に持ち込み、スタジアムは赤色のスティックバルーンで一色に染まりました。これが日本の販促業界から注目を集め、以来、日本のスポーツ観戦にスティックバルーンが使われるようになったと言われています。
中でも浸透しているのがバレーボールで、Vリーグやワールドカップ、春の高校バレーなど、スティックバルーンは応援グッズに欠かせません。
さらに、最近はシティマラソンでの使用も増えています。給水所やゴール付近などで、主催者が「応援にどうぞ」と沿道の観客に無料配布するのが一般的。
シティマラソンは2007年の「東京マラソン」をきっかけに各地で開催されるようになり、大会の増加と平行してスティックバルーンも広まってきています。
知ってて当然!?スティックバルーンの使い方
まだスティックバルーンを使ったことがないという方へ。一体どうやって使うものなのか、ご紹介しましょう。

ストローをスティックバルーンの空気注入口に差し込んで膨らませる
まず袋から取り出し、空気封入口にストローを回しながらゆっくり差し込みます。
次に、ストローで空気を封入します。十分に空気が入ったら、ストローをゆっくり引き抜きます。
最後に、空気注入口の「逆止弁」の先端をしっかり折り曲げて完成です。弁がバルーンに密着することで、空気が漏れなくなります。
実はバルーンの品質はこの「逆止弁」に左右されます。逆止弁は空気を入れても逆流しない性質を持つパーツのことで、品質が悪いとバルーン内の空気が漏れやすくなり、膨らませてもすぐに萎んでしまいます。
使用後は、再びストローを差し込んで、バルーン内の空気を押し出しましょう。ちなみに、バルーンは繰り返し使用できますよ。
名入れスティックバルーンを作るには。デザイン完成までの流れと注意事項
スティックバルーンがどういったものかイメージできたところで、名入れ発注の手順を説明します。
1、ベースとなるバルーンの色を選びます。
2、入れたい文字を決めます。チーム名、ロゴマークなどです。
3、文字の色を決めます。
これだけで、名入れスティックバルーンの完成です!
「いやいや、文字だけでは満足できない!ロゴマークやオリジナルデザインを印刷して、もっとこだわって作りたい!」という場合には、
・ロゴマークなどのデータを送る方法。
・「イラストレーター」や「フォトショップ」などのデザイン編集ソフトを使って、自分で製作する方法。
・手書き原稿やラフ原稿でイメージを伝えて依頼する方法。
などもあります。
片面印刷と両面印刷から選べたり、ロット数が「何個から」と決まっていたりと、印刷業者によって異なる点も多いので、作りたいバルーンをイメージして希望に合った発注先を探してみましょう。

スティックバルーンへのプリント方法は様々
印刷方法は主に3種類
スティックバルーンへの名入れの製法は、主に「シルク印刷」、「昇華転写式インクジェット印刷」、「グラビア印刷」の3種類。
バルーンはポリエチレンフィルムという特殊な素材でできているので、印刷には熟練の技術が必要です。
選手名やシンプルなメッセージを入れるならシルク印刷、フルカラーで小ロットなら昇華転写、フルカラーで大量注文の場合はグラビア印刷、などという具合に使い分けられています。
シルク印刷には製版が欠かせないので、別途版代が必要な場合があります。事前に確認しておきましょう。